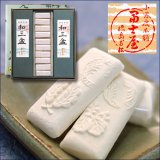大谷焼 ビールジョッキ ドイツジョッキ復刻モデル(刻印なし)

阿波・徳島の伝統工芸「大谷焼」

-
江戸時代後期、安永9年(1780年)に、四国八十八ヶ所霊場の巡礼に来た豊後の国(大分県)の焼き物細工師・文右衛門が、ここ大谷村において、蟹ヶ谷の赤土で作ったロクロ細工を披露し、時の庄屋森是助が、素焼窯を築いて、焼きたてたことが起源と伝えられています。
その昔は、阿波藍を寝かせるための大甕(おおがめ)が盛んに焼かれていた時代もありました。今もその伝統は息づいていて、身の丈ほどもある甕や睡蓮鉢の大物陶器の大きさと、それを焼く登り釜は、日本一と評されています。
近年は民芸調の雑器をはじめ、オリジナリティ溢れる芸術品まで、暮らしの中に息づいてきた素朴な温かさを大切にした作品が次々と生まれています。
平成15年9月に、国の伝統的工芸品に指定されました。
大谷焼の伝統的技法「寝ロクロ」
- 「寝ロクロ」と呼ばれる技は、大谷焼の大物陶器作りの手法です。その名の通り、寝ながら足で蹴り、ロクロを回します。 一定のスピードを保ちながら蹴り上げる技術は熟練の技を必要とします。 阿波藍を寝かせるための大甕(おおがめ)が盛んに焼かれていた時代もありました。身の丈ほどもある甕や睡蓮鉢の大物陶器に「寝ろくろ」技術が使われています。
 |
 |
 |
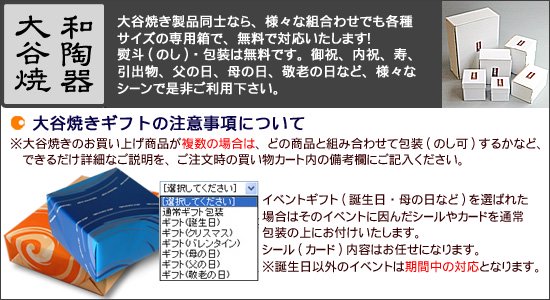
- どっしりとした存在感の中に、温かみのある色合いが美しい、徳島県の伝統工芸品「大谷焼(おおたにやき)」の陶器製品です。
基本の大きさ、色合い、形などは、ほぼ同じですが、職人が一つ一つ手作りで造り上げるため、同じものは一つとしてありません。手作り感漂う温かみのある仕上がりが人気です。伝統の中にも現代の遊び心を感じさせる様々な窯元職人の"心粋"をどうぞお楽しみ下さい。
阿波・徳島県の伝統工芸品「大谷焼」の製品について
映画「バルトの楽園」で使われた「大谷焼ジョッキ」


第一次世界大戦中の徳島県鳴門市の板東俘虜収容所で起きた実話を基に描いた松平健主演の感動ドラマ。
厳しい待遇が当然の収容所の中で、徳島県鳴門市の板東俘虜収容所の所長を務める会津人の松江豊寿(まつえとよひさ)は、陸軍の上層部に背いてまでも、捕虜達の人権を遵守し、寛容な待遇をさせた。捕虜達は、パンを焼く事も、新聞を印刷する事も、楽器を演奏する事も、さらにはビールを飲む事さえ許された。
そして、終戦を迎え、大ドイツ帝国は崩壊する。自由を宣告された捕虜達は、松江豊寿や所員、地域住民に感謝を込めて、日本で初めてベートーベン作曲『交響曲第九番 歓喜の歌』を演奏する事に挑戦したのであった。
撮影には、鳴門に組んだ巨大なOPENセットが、総工費3億円、1万m2の敷地に6ヶ月間かけて【板東俘虜収容所】が再現されました。
大谷焼の窯元は、この【板東俘虜収容所】の近くに点在しています。当時はこの収容所では大谷焼で作られたビールジョッキが使われていたそうです。映画【バルトの楽園】で使われたビールジョッキもまた、大谷焼の窯元からの協力で当時を再現されたました。
- 陶器ならではのどっしりとした重みと、深い温かみのある色合いが美しい、大谷焼/食器/和食器/フリーカップ/ビールジョッキの人気商品です。
仕上がりには鉄黒の釉薬(ゆうやく)を使用しています。砂分が少ないため、ザラザラ感はほとんど無く、光沢がかっています。
基本の大きさ、色合い、形などは、ほぼ同じですが、職人が一つ一つ手作りで造り上げるため、同じものは一つとしてありません。手作り感漂う温かみのある仕上がりが人気です。 -
よく冷やした大谷焼のビアジョッキに、たっぷりビールを注いで豪快に飲み干す・・・器のザラザラ感が滑らかな泡立ちを助け、保冷性もバツグンの陶器の良さは、こだわり派の方などには特におすすめ。
500mlのビールを並々と注ぐと、器とビールのずっしりとした感覚が手に残る・・・ダイナミックに夜の晩酌を是非お楽しみください。
大谷焼 ジョッキ 刻印入り記念版
| 品名 |
|
|---|---|
| サイズ |
|
| 重量 |
|
| 生産地 |
|
| 窯元 |
|
| 仕様 |
|
| 注意事項 |
|
お届けについて
※包装(のし可)するかなど、できるだけ詳細なご用途の説明を、ご注文時の買い物カート内の備考欄にご記入ください。
分類/用途
徳島伝統工芸品/大谷焼き/陶器/焼き物/食器/和食器/お土産(御土産)/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/お祝い(御祝)/内祝/贈答品/粗品/記念品/寿/引出物/結婚祝/祝事/慶事/仏事/バレンタインデー/ホワイトデー/プレゼント





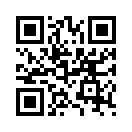
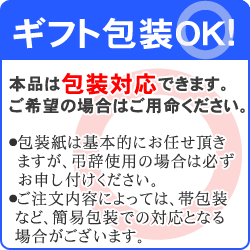
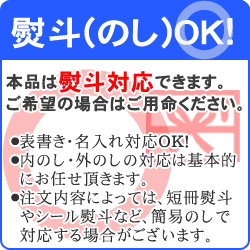





















![半田そうめん1kg 化粧箱入[阿波おどり太口 半田手延べ素麺]徳島県名産品/ギフト/贈答品/お中元/お歳暮/内祝い](https://img02.shop-pro.jp/PA01007/181/product/1485152_th.jpg?cmsp_timestamp=20190322150321)
![半田そうめん2kg 化粧箱入[阿波おどり太口 半田手延べ素麺]徳島県名産品/ギフト/贈答品/お中元/お歳暮/内祝い](https://img02.shop-pro.jp/PA01007/181/product/1485168_th.jpg?cmsp_timestamp=20190322150359)









![<img class='new_mark_img1' src='https://img.shop-pro.jp/img/new/icons25.gif' style='border:none;display:inline;margin:0px;padding:0px;width:auto;' />送料無料 半田手延べそうめん2kg&すだちめんつゆの詰合わせ 箱入り[阿波おどり太口 素麺]徳島県名産品/ギフト/贈答品/お中元/お歳暮/内祝い](https://img02.shop-pro.jp/PA01007/181/product/168677138_th.jpg?cmsp_timestamp=20240410063755)